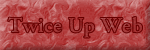
twice up vol.7
方違え(かたたがえ)
仕事帰りに一杯やることを「方違え」と呼ぶ人がいた。
方違えとは、陰陽道の考えの一つで、出かける日に目的地の方角がわるい場合、いったん別の場所に行き、方角をかえてから出かけることである。いにしえの人々は、前夜、吉方にある家に一泊したという。その人は、まっすぐ帰宅せず、寄り道して一杯やっていくことを「方違え」としゃれたわけだ。うまいたとえだと思った。
*
人が酒を飲む理由はいろいろである。
コミックソングで名高いベートーベン鈴木のヒット曲に「日本全国酒飲み音頭」がある。「×月は××で酒が飲めるぞ 酒が飲める飲めるぞ 酒が飲めるぞ」という歌詞をご記憶の方も多いと思う。
「1月は正月で」、「2月は豆まきで」などと、その月の年中行事が織り込まれる。ようするに酒飲みというものは何にでもかこつけて飲んでしまうぞという歌なのだが、よくよく考えてみればただの言い訳である。
酒飲みの立場は弱い。「酒が飲みたいから飲んでるんだ」とは、よほどの豪傑でもなければそうそう言えたものではない。だから理由が必要になる。
そこでわが愛すべき酒飲みたちがひねり出したのが、「付き合い」というウルトラCである。勤め人だったら歓送迎会、打ち上げ、接待といったところか。頭に角をはやした奥さんや、待ちくたびれたガールフレンドに、苦み走った顔で「付き合いでさ」と言ったことがある男性諸君は少なくないだろう。仕事がらみでしぶしぶといったニュアンスが感じられるところがすばらしい。
だが、その「付き合い」が使えない場合がある。
なんでもないのに酒を飲んだときである。
たとえば長谷川町子の『サザエさん』で、会社帰りの波平やマスオさんが駅前の屋台に「引っかかった」とき。帰宅後、二人は必ずフネやサザエさんに「また!」と詰め寄られるが、説得力のある理由などありはしないから、「ちょっとぐらいいいじゃないか」などとすねてみせるのである。しかし、しばしばそんな気まずい思いをしているだろうに、二人が屋台通いをやめる気配はない。なぜか。ここは波平やマスオさんが誰と誘い合わせるでもなく、それぞれひとりで飲んでいることに注目したい。
彼らは酒が飲みたいというより、ひと息つきたいのである。
*
どんな人でも酒場では等しく「客」である。職業人でもなく家庭人でもなく、束の間、見知らぬ人と肩を並べて過ごす。ほのかな酔いとともに、ゆるやかにきょうという日がリセットされてゆく。
女性だって例外ではない。いつのころからか、「女がひとりで行ってもだいじょうぶなお店はありませんか」と訊かれることが多くなった。そんなときわたしは迷わず、心優しいバーテンダーがいるオーセンティックバーをおすすめすることにしている。
*
方違えで、出かける前夜に一泊する家を「方違え所」という。どうやってその家を決めていたのかはわからないが、清少納言が『枕草子』で「方違へにいきたるに、あるじせぬ(もてなさない)所」とくさしているから、まったく知らない人の家というわけでもなかったのだろう。清少納言のライバル紫式部は『源氏物語』で、光源氏が方違えを理由に女を訪ね歩くさまを描いている。
なんて蘊蓄を傾けてみたところで「またわけのわからないことを言って!」とうるさがられるのが関の山なのだが、酒を飲んで咎められるうちはシアワセ、と思うことにしようではないか。
男でも女でも、家族があってもなくても、だれだってひと息つきたくなることがある。
わたしに方違えのたとえを教えてくれた人は、きっと今夜もどこかで一杯やっているにちがいない。
(2003.6.28 H.S.)
Copyright©2004 by Twice Up Web.
All rights and seats reserved.